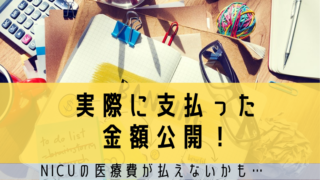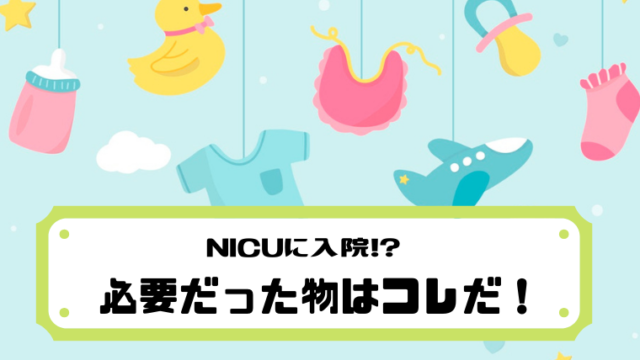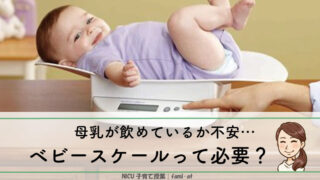低出生体重児で産まれたお子さんの場合、必ず低出生体重児で産まれたことを申請しておく必要があります。
その理由について詳しく解説していきます。
低出生体重児の体重はどれくらい?
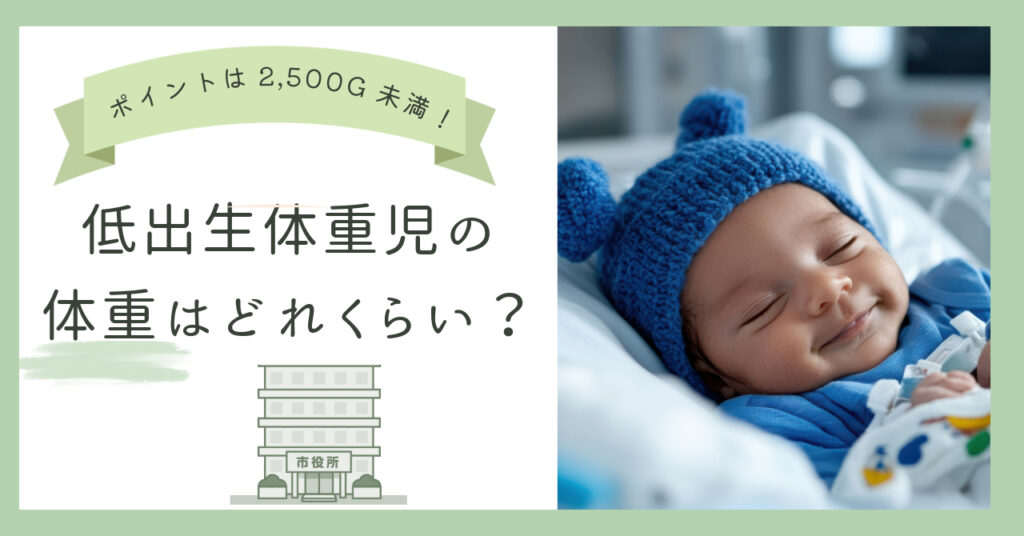
低出生体重児とは、その名の通り「体重が小さく産まれた赤ちゃん」を指します。
2,500g以上4,000g未満で産まれる「正出生体重児」の赤ちゃんは、基本的に正常な状態で産まれてきたと言えます。
逆に、4,000g以上で産まれた大きな赤ちゃんは「高出生体重児」と呼ばれ、昔でいう「巨大児」とも呼ばれる状態で、大き過ぎることでリスクや合併症の危険があります。
低出生体重児は「2,500g未満」で産まれた赤ちゃんのことです。
我が子のように940gで産まれた赤ちゃんのことを「超低出生体重児」と呼び、1,500g未満の赤ちゃんは「極低出生体重児」と呼ばれます。
そのため、「超低出生体重児」も「極低出生体重児」も低出生体重児として届出が必要です。
低出生体重児の届出はなぜ必要?

低出生体重児は「正出生体重児」とは異なり、生後体重が2,500g未満の赤ちゃんは住民票のある市町村に届出を出す必要があります。
これは、母子保護法第18条に基づくため、届出の義務があります。
低出生体重児の届出を行うことで、保健センターのサポートや助産師・保健師の訪問の際にも低出生体重児として対応してくれます。
低出生体重児の届出はどこに提出?市町村で良い?
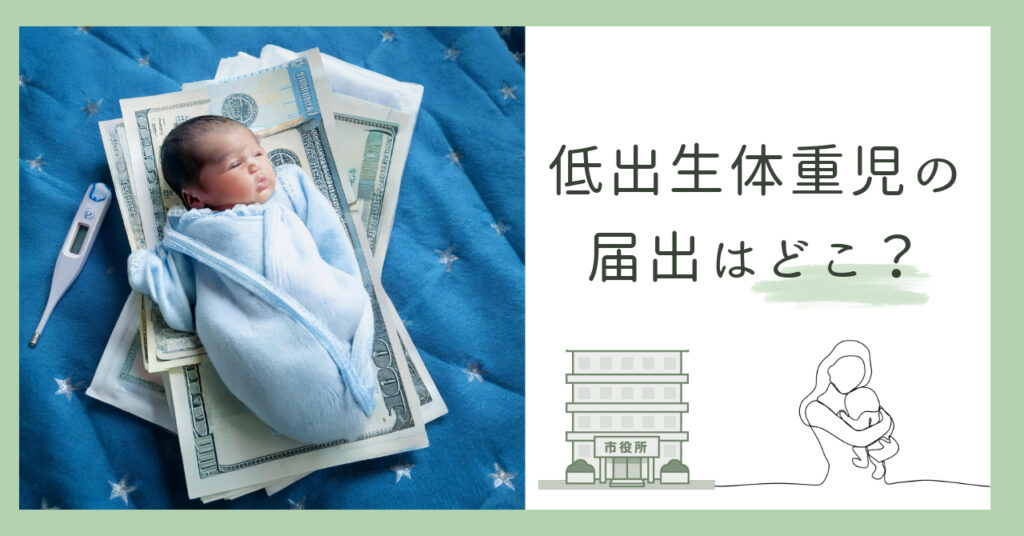
低出生体重児の届出は、母子手帳を交付してもらった市町村に行う必要があります。
そのため、母子手帳を交付した市町村ではない市町村で里帰り出産などを行った場合には、出生届の提出と一緒に低出生体重児の届出を行うのがベスト。
低出生体重児を出産したお母さんの場合、入院日数が通常よりも伸びる場合もあります。
できれば、お父さん(旦那さん)や家族と連携をとって各市町村へ低出生体重児の届出を行いましょう。
未熟児養育医療給付は低出生体重児の届出とは違う!医療費負担を減らす?

低出生体重児の届出とは別に、未熟児養育医療給付の申請書類を病院から受け取ったひとは必ず各市町村へ提出しましょう。
入院養育が必要と認められた指定養育医療機関に入院している低出生体重児で、出産時の体重が2,000g以下のお子さんに対して、治療に必要な医療費を公費で負担する制度になります。
入院中の医療費のうち、保険診療分の自己負担額と食事療養費(いわゆるミルク代)が対象です。
ただし、差額ベッド代などの保険対象外は除くので、注意しましょう。
一部、市町村民税額に応じて自己負担になる場合もありますが、子ども医療費の対象になるので、自己負担額を抑えることができます。
退院後の申請はできないので、必ず入院中の申請が必要です。
医療機関の主治医に養育医療意見書を作成してもらう必要があるので、もし出生時の体重が2,000g以下なのに申請書類について案内されていない…という人は主治医に相談しましょう。
- 養育医療申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 住民税・県民税証明書(該当者のみ)
- 委任状
- 子ども医療費受給者証
- お子さんの健康保険証(加入手続き中は加入予定の健康保険書でも可能な場合があります)
- マイナンバー(お子さんと扶養義務者全員)
通院の場合は対象にならず、指定養育医療機関でなければ利用できないです。
基本的には医療機関や主治医から案内があります!費用面で不安を抱えなくても良いように、必ず申請を行いましょう。
医療費については、以下の記事も参考にしてみて下さい。
まとめ
低出生体重児の提出は義務付けられているので、必ず申請を行いましょう。
- 申請は母子手帳交付の市町村
- 2,000g以下は未熟児養育医療給付の申請も
- 旦那さんや家族と連携で忘れず提出
不安なことも多い、低出生体重児のお母さん。
私も実際に分からないことが多く、市役所の窓口の人と「あれは?」「これは?」と少し面倒な住人だったと思います。
赤ちゃんを小さく産んでしまった罪悪感がある中での申請は、現実を突きつけられているようで、正直しんどかった…。
できれば、旦那さんや自分のご両親など、信頼できる人と手続きをするのがおすすめです。
低出生体重児の提出をしておけば、保健センターも情報共有してくれます。私の場合は赤ちゃんが退院するまで電話をくれました。
今の自分の不安はもちろん、「どんな治療を今行っているのか」「こんなことができるようになっていた」と、嬉しいことも共有できたので気持ちもスッキリ。
安心して子育てするためにも、必ず申請をしておきましょう。